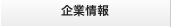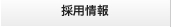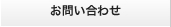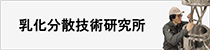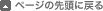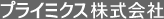Today's Notables 2005年04月
JQAへの取り組み
代表取締役社長 古市 尚
 現在弊社では日本経営品質賞、英名JQA(Japan Quality Award)に取り組みはじめている。JQAは財団法人社会経済生産性本部で運営している経営品質協議会が、年度毎に国内で経営品質の最も優れた企業に贈る賞のことである。そもそも、この賞が日本で設定されたのは、1988年にアメリカで発足された「アメリカ国家品質賞」、別名「マルコム・ボルドリッジ賞」に端を発している。敗戦直後の日本は廃墟の中から立ち上がり、もの作りを再開したが、当初は粗悪品、コピー品、ものまねの代名詞として「メイド・イン・ジャパン」という言葉が使われていたほどだった。しかし、勤勉な国民性は欧米の先進技術を学び、生産に取り入れる技術力に長けており、世界を感嘆させるスピードで、上質なクオリティの製品を世の中に送り出す国となった。1979年に出版された、当時ハーバード大学教授のエズラ F. ヴォーゲル氏著による「ジャパン・アズ・ナンバーワン」に象徴されるように、70年代後半から日本の電化製品や自動車などに代表される日本の工業製品は「メイド・イン・ジャパン」のマイナスイメージを払拭し、信頼のブランドへと変革を遂げたのである。中でも日本企業は顧客と市場のニーズを的確に捉え、生産効率の向上や製品品質の改善をスピーディーに、しかも継続的に行うことに優れており、他国のもの作りを卓越する体制を作り上げたのである。
現在弊社では日本経営品質賞、英名JQA(Japan Quality Award)に取り組みはじめている。JQAは財団法人社会経済生産性本部で運営している経営品質協議会が、年度毎に国内で経営品質の最も優れた企業に贈る賞のことである。そもそも、この賞が日本で設定されたのは、1988年にアメリカで発足された「アメリカ国家品質賞」、別名「マルコム・ボルドリッジ賞」に端を発している。敗戦直後の日本は廃墟の中から立ち上がり、もの作りを再開したが、当初は粗悪品、コピー品、ものまねの代名詞として「メイド・イン・ジャパン」という言葉が使われていたほどだった。しかし、勤勉な国民性は欧米の先進技術を学び、生産に取り入れる技術力に長けており、世界を感嘆させるスピードで、上質なクオリティの製品を世の中に送り出す国となった。1979年に出版された、当時ハーバード大学教授のエズラ F. ヴォーゲル氏著による「ジャパン・アズ・ナンバーワン」に象徴されるように、70年代後半から日本の電化製品や自動車などに代表される日本の工業製品は「メイド・イン・ジャパン」のマイナスイメージを払拭し、信頼のブランドへと変革を遂げたのである。中でも日本企業は顧客と市場のニーズを的確に捉え、生産効率の向上や製品品質の改善をスピーディーに、しかも継続的に行うことに優れており、他国のもの作りを卓越する体制を作り上げたのである。一方、アメリカでは1980年代から工業製品の競争力が次第に失われ、その原因の追求と克服のために商務省をあげて著名な経営学者などの専門家を集め、そのメンバーらによって多くの研究が行なわれた。当然のことながら日本の優れた生産活動は大いに研究され、その他にも様々な側面からアメリカ製品の競争力低下に対する研究がなされた。こうした研究結果をベースに、企業の総合力を共通の物差しを使って審査する賞として1988年に設定されたのが「マルコム・ボルドリッジ賞」である。名称の由来は当時(レーガン政権時代)の商務長官の名前であるマルコム・ボルドリッジからきている。アメリカがこのような国家品質賞を設け、起死回生の努力をする中、日本ではバブル経済の崩壊や世界市場構造の急激な変化などが各業界に打撃を与え、経営の抜本的な見直しを迫られることになる。今度は日本がどうやって経営の抜本的な見直しをすればいいのかを検討しなければならない立場となり、その結果として生まれたのがJQAであると言える。品質マネジメント・システムISOも日本の品質の高さを基準に研究されて作られたものと言われているが、このJQAも、そもそもの基準は日本の卓越した企業をモデルとして作られている。
前置きが少し長くなったが、弊社ではそのJQAをひとつの目標とした取り組みを行っている。JQAではセルフアセスメントと呼ぶ自己診断を行なうのだが、まず、セルフアセスメントができる人間を養成する必要がある。それらの講習会は東京や大阪などで随時行なわれており、先陣を切って私自身がセルフアセッサーの講習を受けることにした。セルフアセッサーの講習はグレード1からG1(1日)、G2(2日間)、G3(3日間)となっており、最終的に認定講習(2日間)を受ければ日本経営品質協議会認定のセルフアセッサーになれる。講習会ではセルフアセスメントのガイドラインや概要を勉強するが、ほとんどの時間がグループワークなどの実習などで構成され、実務に則した演習が行われる。ケーススタディブックを元にグループワークを行うのだが、宿題も多く、久しぶりに普段使っていない方の脳を使うハメになり、それなりに大変だった。
JQAではそれぞれの企業のレベルでどうすれば経営品質が上がるかということを、ダイアログ(対話)を通して合議することが基本となっているが、「正解」というものがないので、講師の説明を聞くたびに考え込まされ混乱もしてくるので、自分なりに咀嚼することが必要である。今後は社内にセルフアセッサーを数人養成し、経営品質の向上に努めていく所存である。
HOME > 最新情報 > Today's Notables > 詳細